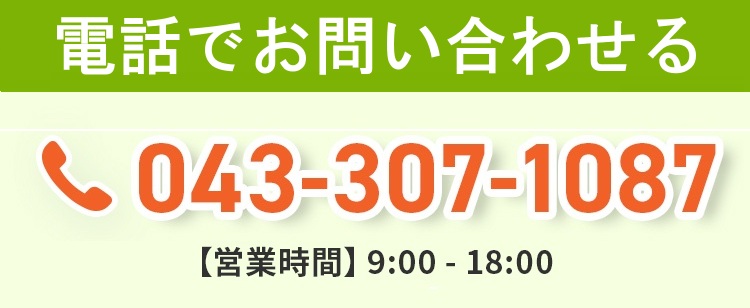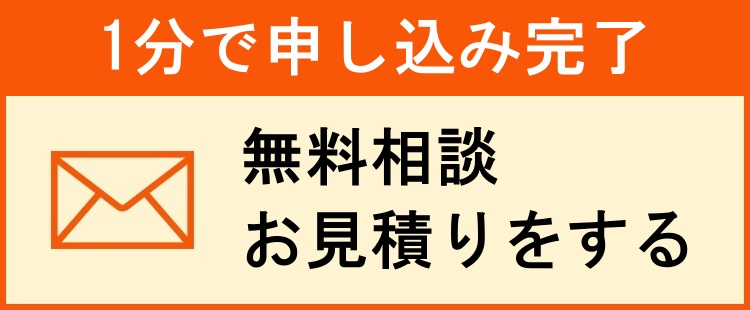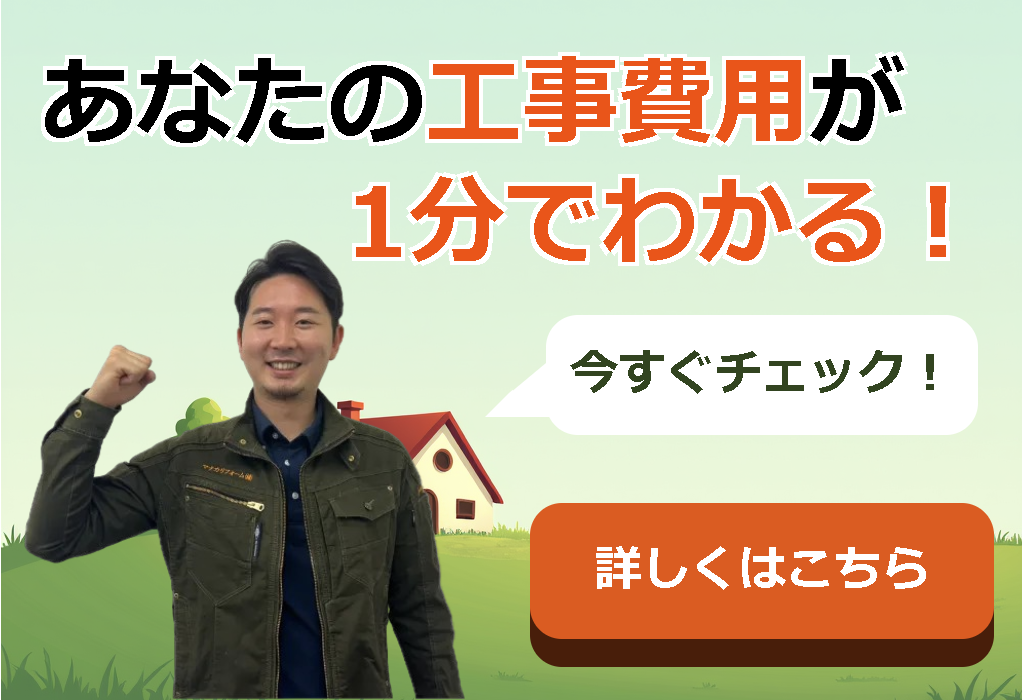屋根塗装の施工事例

マナカリフォームが施工した
事例の一部をご紹介いたします

お気軽にご相談・
お問い合わせください!

外壁


屋根


防水


専門スタッフが、親身にお話を伺います!